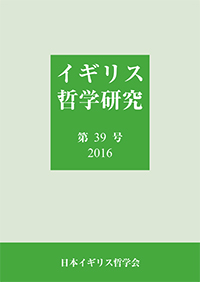
Table of Contents
辞
『イギリス哲学研究』は日本イギリス哲学会の機関誌として世にいう 「紀要」あるいは「年報」と性格を同じくする。期するところは会員の独自かつ清新な研究成果を収載して学的生活の里程標たらしめるとともに学会自体の旺盛な活動を具象化することにある。さらに、本誌はこれを学会内部の閉鎖的領域にとどめず、広く同学の士に解放して学会に寄与する道を開いてある。生誕したみどり児の弛みない質実な成長を期待してやまない。
日本イギリス哲学会
大槻春彦
投稿論文の公募について
『イギリス哲学研究』の投稿論文の公募を受けつけています。詳しくは、各種公募をご参照下さい。
電子公開について
2018年3月30日より、J-STAGEのプラットフォームを利用する形で、『イギリス哲学研究』を電子公開いたしました(第1号(1978年)から第42号(2019年)まで公開済み)。詳しくは、こちらをご覧下さい。以下のURLから閲覧いただけます(2018年4月12日、2020年5月7日追記)。
www.jstage.jst.go.jp/browse/sbp/-char/ja
最新号 第48号(2025年)目次
| タイトル | 著者 | ページ |
|---|---|---|
| 記念講演 | ||
| 精神疾患・医師・患者の構造――19世紀前半イングランドと20世紀前半日本の比較 | 鈴木 晃仁 | 5-18 |
| 論文 | ||
| 「分析」概念と形而上学――R・G・コリングウッドと1930年代イギリスの分析哲学 | 春日 潤一 | 19-37 |
| 感覚の恒常的可能性――ミルの形而上学 | 鈴木 英仁 | 39-57 |
| アダム・スミスと表現の自由 | 山本 陽一 | 59-75 |
| 書評 | ||
| 太田浩之『アダム・スミスの道徳理論――人間の複雑性と道徳判断』 | 篠原 久 | 77-79 |
| 冨田絢矢『道徳はなぜ価値判断の問題になるのか――ヘアの道徳哲学と好敵手たち』 | 蝶名林 亮 | 80-82 |
| 三浦基生『法と強制――「天使の社会」か、自然的正当化か』 | 濱 真一郎 | 82-85 |
| 矢嶋直規編『近代英国哲学とキリスト教神学』 | 門 亜樹子 | 86-88 |
| 渡辺一樹『バーナード・ウィリアムズの哲学――反道徳の倫理学』 | 澤田 和範 | 89-91 |
| ピーター・シンガー編(森村進監訳)『何か本当に重要なことがあるのか? ――パーフィットの倫理学をめぐって』 | 安倍 里美 | 92-94 |
| ウォルター・バジョット(遠山隆淑訳)『イギリス国制論 (上・下)』 | 平石 耕 | 95-97 |
| バーナード・マンデヴィル(壽里竜訳)『名誉の起源 他三篇』 | 林 直樹 | 98-100 |
| Daisuke Arie, Masatake Okubo, Naoki Yajima (eds.), Joseph Butler: A Preacher for Eighteenth-Century Commercial Society | 柘植 尚則 | 101-103 |
| Elad Carmel, Anticlerical Legacies: The Deistic Reception of Thomas Hobbes, c. 1670-1740 | 郷家 綾 | 104-106 |
| Jamison Kantor, Honor, Romanticism, and the Hidden Value of Modernity | 大石 和欣 | 106-109 |
| John Robertson (ed.), Time, History, and Political Thought | 壽里 竜 | 109-111 |
| P. Singer and C.-H. Shih, The Buddhist and the Ethicist: Conversations on Effective Altruism, Engaged Buddhism, and How to Build a Better World | 伊勢田 哲治 | 112-114 |
| 国際学会報告 | ||
| 50th International Hume Society Conference, Hume: Past, Present, and Future, Wadham College, University of Oxford, July 1-6, 2024 | 井上 治子 | 115-121 |
| 国際アダム・スミス学会東京大会 (11-13 March, Waseda University, Tokyo) | 太田 浩之 | 122-127 |
| 【再掲載(校正ミス改訂分)】 第47回大会報告 ※『イギリス哲学研究』第47号、152-159頁。 | ||
| シンポジウムⅡ J・S・ミル研究の現状と意義――没後150周年記念 | 鈴木 真・小沢 佳史・ 村田 陽・成田 和信・ 舩木 恵子 | 129-136 |
| 第48回大会報告 | ||
| シンポジウムⅠ カントと20世紀イギリス哲学――生誕300周年記念 | 佐藤 岳詩・渡辺 一樹・安倍 里美・大谷 弘 | 137-142 |
| シンポジウムⅡ PPE(Philosophy, Politics, & Economics)という学問領域の可能性 ――イギリス哲学の総合性の現代的翻案―― | 平石 耕・児玉 聡・ 中井 大介・久米 暁・ 小林 麻衣子 | 142-148 |
| セッションⅠ イギリス経験論における言語論 | 山川 仁・小田 崇晴・ 西内 亮平・竹中 真也 | 148-155 |
| セッションII 18世紀思想史研究における複合国家論の可能性 ――バーク・ヒューム・フランクリンに着目して―― | 竹澤 祐丈・桑島 秀樹・森 直人・片山 文雄・ 村田 陽 | 155-163 |
| 部会研究例会報告 | ||
| 第113回関東部会 | 高原 亮・三浦 基生 | 165-167 |
| 第70回関西部会 | 貫 龍太・岡本 慎平 | 167-169 |
| 第114回関東部会 | 鈴木 奨・濵野 倫太郎 | 169-171 |
| 第71回関西部会 | 山尾 忠弘・星 太郎 | 172-174 |